 一講演目は、動物園ライターの森由民さんの発表でした。
一講演目は、動物園ライターの森由民さんの発表でした。由民さんが訪れたベトナムにあるハノイ動物園の写真を追いながら、来園者による餌やり問題に触れられ、動物園での展示や飼育について考えさせられるお話でした。
2011年4月30日(土) 環境パートナーシッププラザ セミナースペース
震災の影響によって延期となっていたサポーター発表会が、4月30日地球環境パートナーシッププラザで行われました。
お茶とお菓子がふるまわれ、演者と聴講者の距離が近い和やかな会でした。
この発表会の貴重なお話のほんの一部をお伝えいたします。
1、 森由民さん 可愛くって食べさせたい
 一講演目は、動物園ライターの森由民さんの発表でした。
一講演目は、動物園ライターの森由民さんの発表でした。
由民さんが訪れたベトナムにあるハノイ動物園の写真を追いながら、来園者による餌やり問題に触れられ、動物園での展示や飼育について考えさせられるお話でした。
 ハノイ動物園は必ずしも動物たちにとって住み心地の良い飼育をしているとは言えないかもしれませんが、来園者にとっては動物と人間の距離が近くて楽しく感じる動物園なのだと思いました。しかし動物と人間の距離が近いがために、来園者は可愛さあまって動物に人間の食べ物を与えてしまうそうです。由民さんは、餌を与えるのは動物たちが食べる姿や動きが可愛かったり興味深かったりするからである、という考えから、餌を与えるところを展示することを提案なさっていました。ただ、その展示がお客さんを楽しませるためだけのショーとなることや、来園者にとっては餌をやる娯楽からおもしろい動きを見る娯楽へと変わるだけなのでは、という懸念もなさっていました。
ハノイ動物園は必ずしも動物たちにとって住み心地の良い飼育をしているとは言えないかもしれませんが、来園者にとっては動物と人間の距離が近くて楽しく感じる動物園なのだと思いました。しかし動物と人間の距離が近いがために、来園者は可愛さあまって動物に人間の食べ物を与えてしまうそうです。由民さんは、餌を与えるのは動物たちが食べる姿や動きが可愛かったり興味深かったりするからである、という考えから、餌を与えるところを展示することを提案なさっていました。ただ、その展示がお客さんを楽しませるためだけのショーとなることや、来園者にとっては餌をやる娯楽からおもしろい動きを見る娯楽へと変わるだけなのでは、という懸念もなさっていました。
可愛くて食べちゃいたい、だとか、可愛くて食べさせたい、だとか人間はなんとも勝手なものです。でもその人間の感情を否定せずに、動物園が動物と来園者どちらにとってもぴたりとはまるような場所になるよう、悩み続けるのが大事なことなのだと感じました。
2、 木村奈津子さん ユキヒョウを守るとはどういうことか:海外組織による域外保全の取り組みから
 二講演目は一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程の木村奈津子さんの発表でした。
二講演目は一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程の木村奈津子さんの発表でした。
海外のユキヒョウ保護団体や動物園のユキヒョウ保護の取り組みから、動物園とユキヒョウ保護の関係や難しさについて詳しくお話なさっていました。
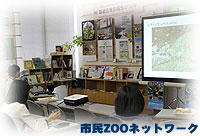 木村さんが訪れたスウェーデンのNordens Arkという保護施設とアメリカのWOODLAND PARK ZOO でのユキヒョウ保護活動の紹介がありました。本筋とはそれますが、Nordens Arkでのもとの地形をいかした広大な施設に一度は訪れてみたいと、その場にいた誰もが感じたと思います。希少種の繁殖や、生息地のユキヒョウ調査の事前準備としてユキヒョウに首輪をつけて支障がないか確認することが行われているそうです。また世界の動物園で飼育しているユキヒョウは地球上に生存しているユキヒョウの6〜20%を占めるそうです。このことから、ユキヒョウがいかに希少な動物であり動物園での域外保護が生息地での域内保護を支えているかということを知りました。しかし一方で、動物園での保護では多様性の欠如の問題や、個体への配慮が保護に繋がることをイメージしにくいこと、希少種の展示によって来園者が保護に関心をもつのか、といった難しさがあることも知りました。
木村さんが訪れたスウェーデンのNordens Arkという保護施設とアメリカのWOODLAND PARK ZOO でのユキヒョウ保護活動の紹介がありました。本筋とはそれますが、Nordens Arkでのもとの地形をいかした広大な施設に一度は訪れてみたいと、その場にいた誰もが感じたと思います。希少種の繁殖や、生息地のユキヒョウ調査の事前準備としてユキヒョウに首輪をつけて支障がないか確認することが行われているそうです。また世界の動物園で飼育しているユキヒョウは地球上に生存しているユキヒョウの6〜20%を占めるそうです。このことから、ユキヒョウがいかに希少な動物であり動物園での域外保護が生息地での域内保護を支えているかということを知りました。しかし一方で、動物園での保護では多様性の欠如の問題や、個体への配慮が保護に繋がることをイメージしにくいこと、希少種の展示によって来園者が保護に関心をもつのか、といった難しさがあることも知りました。
木村さんがおっしゃっていたように、ユキヒョウ生息地で生活する人間の考え方、動物園の考え方、保護施設の考え方、保護というひとつの物事に対するたくさんの考え方を知ることがとても大切であることを学びました。
3、 斎藤健太さん 川崎市夢見ヶ崎動物公園について
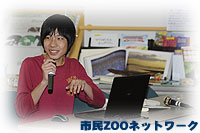 三講演目は象学生の斎藤健太さんの発表でした。
三講演目は象学生の斎藤健太さんの発表でした。
象学生とは、象が大好きな中学生、の簡略バージョンだそうです。
 そんな愉快な自己紹介から始まり、斎藤さんがよく訪れる夢見ヶ崎動物公園に暮らす動物たちを、レッサーパンダから始まりニワトリまで全てを写真とともに紹介してくださいました。中でもヤマシマウマの親子三個体の紹介が印象的でした。三個体の見分け方や、性格の相違を詳しくお話してくださり、写真を見ているだけなのにシマウマそれぞれが目の前で動き出すように感じました。
そんな愉快な自己紹介から始まり、斎藤さんがよく訪れる夢見ヶ崎動物公園に暮らす動物たちを、レッサーパンダから始まりニワトリまで全てを写真とともに紹介してくださいました。中でもヤマシマウマの親子三個体の紹介が印象的でした。三個体の見分け方や、性格の相違を詳しくお話してくださり、写真を見ているだけなのにシマウマそれぞれが目の前で動き出すように感じました。
夢見ヶ崎動物公園は入場料無料で、その土地に暮らす人間の通学路や散歩道になっているそうです。日常の中に様々な動物の姿があって、動物がいる暮らしが当たり前の中でまっすぐに成長して、楽しそうにその動物たちの紹介をする、象学生の斎藤さんにあこがれを感じました。
 全ての講演終了後に、お楽しみプログラムでペンギンクイズがありました。どの問題も難しくマニアックでしたが、みごと高得点獲得者の方はプレゼントをゲットしていらっしゃいました。私も次回はプレゼントに少しでも近づけるように、今日の発表会をはじめ日々動物、動物園に心を留めて過ごそうと思いました。
全ての講演終了後に、お楽しみプログラムでペンギンクイズがありました。どの問題も難しくマニアックでしたが、みごと高得点獲得者の方はプレゼントをゲットしていらっしゃいました。私も次回はプレゼントに少しでも近づけるように、今日の発表会をはじめ日々動物、動物園に心を留めて過ごそうと思いました。
(エンリッチメント大賞2011スタッフ/日本獣医生命科学大学5年 田中 優)
(写真撮影:大木正美)